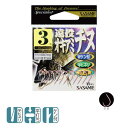チヌ・クロダイ用おすすめの針の号数(サイズ)と種類をみていきます。
チヌ針は万能な針であり、チヌだけでなく、淡水魚やワームのフックとしても使われています。
そんなチヌ針の用途に合わせた使い方ができれば釣果もアップすることでしょう。
目次
チヌ針の特徴は?

まずチヌ針にはどんな特徴があるのかを見ていきましょう。
使用するエサや場所、状況によってうまく針を使い分けることが釣果に繋がります。
チヌ針とは
針の基本型と言われる伊勢尼(いせあま)という針によく似ているが大きな特徴です。
軸(針の線型)が細く無駄な重さを持ちません。チヌ・クロダイに最適な針の形状で、チヌの口元に針を掛けるというよりも飲み込ませるために針を軽くしています。
チヌは貝殻を砕くほど歯が強く、口元が固くなっています。
そのため、針を軽くして飲み込ませて釣る様な形状になっています。
ヒネリというチヌ針に多い形状は、吸い込んで吐き出す時に回転してかかりやすくなっています。
チヌ針の色は?
チヌ針にも様々な色があります
金色・ゴールドの針
濁りがあったり、天候が悪く光が差し込まない時に使います。サシエを目立たせる効果があります。しかし、エサ取りが多いときには、目立つことですぐにサシエをとられてしまいます。喰いの渋ったときに使いましょう。
黒色・茶色の針
目立ちにくく、エサ取りをかわすのに使います。また、警戒心の強い魚に対して有効ですので、チヌ釣りに向いている色です。
白・ピンクの針
ボイルカラーやオキアミカラーと言われる針で、オキアミとどうかすることでさらに警戒心を解いて使うことができます。使うオキアミがボイルか生オキアミかによって同化しやすい色を選ぶとよいでしょう。デメリットとしては、塗装が施してあるため、針自体が高価です。
蛍ムラカラーの針
ケイムラは紫外線に反応して発光する塗料が塗られており、日中の深い場を狙い、サシエを光らせて目立たせたいときに使用します。
夜光(グロー)の針
蓄光することのできる針です。夜間や深場でエサを目立たせるのに使います。針からサシエが外れていても、ルアー効果で、光る針に魚が食いついてくることもあります。警戒心の強い魚は近寄らないこともあります。
チヌ針の号数は?
1号から5号ぐらいまでのサイズで大きさに迷う方もいらっしゃるかと思います。
とりあえずチヌ針一袋買うならお勧めするのはチヌ針の2号です。
一般に販売されているオキアミの大きさにちょうどよく、ネリエやさなぎにも使え、20cm~50cmぐらいのチヌにも対応できます。
もし、もう一袋買うのであればチヌ針の1号とします。この理由としては、チヌが釣れすぎて困るということはなかなかありません。
むしろ、今日は一匹も釣れないとなることのほうが多いように思います。
そんな渋い中でもチヌのアタリを出すために、小さくて違和感のないチヌ針1号を持っておくとよいでしょう。
オキアミを剥き身にして使うと小さくなります。チヌ針の1号がこれにちょうどよいサイズです。
結局どれを買えばいいのか?
これからチヌ針を買いに行くのにどれを買おうかを迷っている方にとりあえずこれで安心といった針をご紹介します。
掛かりすぎチヌ
とにかく針がチヌにかからなければ意味がありません。
針が刺さることを大前提に貫通力を強化したがまかつのかかりすぎチヌがあればひとまず安心です。
それ以外には、どのような釣り場かによって、エサ取りや状況に応じて使い分けるように針を準備してみましょう。
釣り針ケースにマグネットシートを装着。落下防止のフックケースのおすすめ紹介