カワハギ釣りは、その美味しさと釣りの奥深さで多くの釣り人に人気があります。
また、カワハギはおちょぼ口で餌を巧みに摂取することから、「エサ取り名人」とも呼ばれ、釣るのが難しく、釣れると楽しい、食べておいしい魚です。
そんなカワハギ釣りのおすすめの集魚剤を厳選しましたので見ていきましょう。

目次
カワハギ釣りの集魚剤の重要性と使い方

カワハギ釣りにおける集魚剤の使用は、カワハギを効率的に寄せ、釣果を高めるために非常に重要です。
魚自体がそれほど大きくないので、数釣りを楽しむのがよく、たくさん釣るためにも魚をたくさん寄せてコンスタントに釣り続けるのがいいでしょう。
集魚剤なしでもカワハギは釣れますが、回遊性があまりない魚なので、自分の釣りのポイントに集魚剤を使って魚を集めたほうが釣りやすくなります。
カワハギは好奇心旺盛で、匂いや味に惹かれやすいです。
特に、専用で作られたアサリエキス配合の集魚剤は、カワハギが大好きなアサリの汁や香りがついているので、魚がよく寄ります。
カワハギ釣りにおすすめの集魚剤
マルキュー カワハギまきえ

特徴
特徴: 波止・堤防対応、海水不要のウェットタイプ、すぐに使える (マルキュー)
波止や堤防、小磯、筏やカセでの釣りに特に適しており、カワハギが好むアサリエキスが含まれています。
1,000gという大容量で、ウエットタイプなので開けてすぐに使えます。
チャック付き袋で乾燥を防ぎ、持ち運びも簡単です。
握り加減で撒き餌のバラケ具合が変えられるので、底にカワハギを集めたい場合はしっかりと握り、中層に浮かせたい場合は軽く握って使い、状況に応じて使い分けられる餌になっています。
ヒロキュー にぎってポン カワハギ専用
特徴
特徴: 味と視覚のダブル効果、カワハギの好物配合
主成分はカワハギの好むアサリエキスに加え、オキアミミールや魚粉がブレンドされています。
これにより、魚の好奇心を刺激し、集魚効果を高めます。
さらに、視覚効果を考慮して、光を反射する大きな光物のキラリと白く目立つ押し麦を加えました。この特別なブレンドは、波止やイカダ、ボート釣りにも適しています。
手軽さと効果の両方を兼ね備えており、九州では人気の製品です。
ダイワ(DAIWA) 集寄 寄せ魂カワハギ15 各種
特徴
特徴: 強力な匂い、長時間寄せる、新発想のカワハギ釣り用集魚剤 (ダイワ)
鯉釣りのボイリーのような餌で、海に撒いて使うのではなく、仕掛けに装着して使います。
徐々に溶けだして匂いで誘うことができ、撒き餌の届かない水深の深い釣り場で重宝します。
必ずしもカワハギだけに効果的というわけでもなく、フグなども寄ってきます。
使い方を選びますが、アタリのない日などに使ってみるのもいいでしょう。
おすすめはアタリ数が多くなるエビのフレーバーです。
季節に応じたカワハギ釣り
カワハギは通年釣ることが可能ですが、季節によって最適な釣り場所やターゲットのコンディションが異なります。
夏場は堤防、磯、サーフでの釣りがおすすめで、特に7月~8月は活性もよく浅瀬でも釣りやすいです。
冬場は船釣りが主流で、11月~2月はカワハギの肝が特に大きくなります。
朝マズメや満潮の時間帯が狙いやすいとされています。
カワハギの生態と生息地
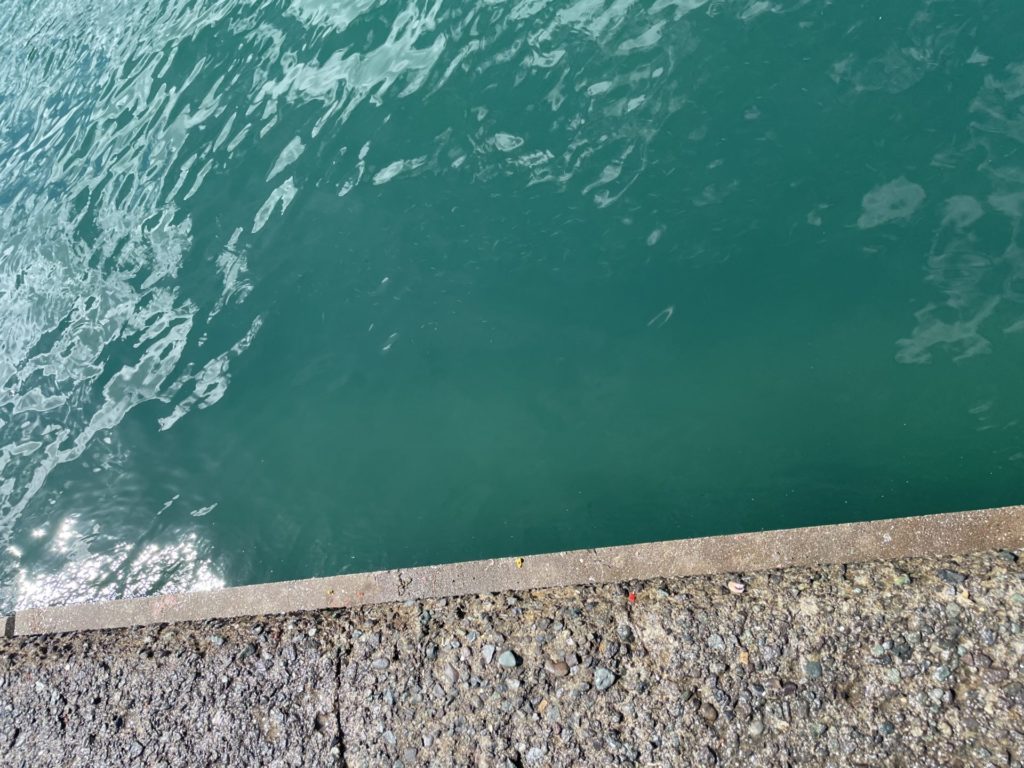
カワハギは海底の砂地と岩礁がある場所に生息しており、甲殻類やイソメ類を主食としています。
この習性を利用した投げ釣りや胴付き仕掛けの釣り方が一般的です。
まとめ
北海道から南の海域に広く生息するカワハギは、特に冬場の肝が絶品で、海のフォアグラとも称されます。
カワハギ釣りは、魚の生態や季節ごとの状況を理解することが重要です。
また、集魚剤を使って魚を寄せることで釣りやすくなるため、初心者の方や何としてもカワハギを釣りたい人には集魚剤を使って欲しいものです。集魚剤は、釣りのチート技とも言えます。
カワハギ釣りは技術と知識が要求される釣りですが、その分、釣れた時の喜びも大きいでしょう。
釣りを楽しむ際にはこれらのポイント覚えておき、美味しいカワハギを釣りを楽しんでみてはいかがでしょうか。
撒き餌や集魚剤だけでなく、付け餌も重要になります。
カワハギ釣りの集魚剤については以下の記事もご参照いただければ幸いです。
カワハギ釣りの餌紹介: アサリ以外にも釣れる最強の餌がある!
業務スーパーで買える釣りエサの代用品とおすすめの使い方。釣れる魚



